|
|
| |
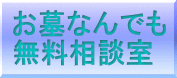 |
 |
| ガンコマサ 施工例 |
| |
||
| 石碑は、建之されたときはただの石に過ぎず、仏様・ご先祖様をお迎え入れる為の 開眼法要という儀式を済ませて初めて石碑は礼拝の対象となります。 また納骨法要とは、お亡くなりになった故人のお骨をお墓に納める法要のことです。 ですから先ずお墓を立てられたときは、これらを一緒に行います。 寿陵墓の場合、お墓に納めるお骨はなくても、 ご先祖様をお迎えする開眼法要の儀式は行います。 |
||
| 法要の流れ |
|
|||||
| |
親戚などが集まりやすい良い日を選び 早い内にお寺様に依頼をしておきましょう。 (特にお彼岸・お盆はお寺様が忙しいときなので、 早い目にご予約した方がよいでしょう。) 当社でお寺様のお手配もさせて頂きます。 |
||||
|
|||||
海の物・・わかめ、昆布など 山の物・・干し椎茸、山芋、栗など 里の物・・高野豆腐 大根 にんじん 果物など その他お酒・お餅・お塩・お花 (開眼用赤ローソク・お骨袋・お焼香道具・等は 石材店でご用意できます。) |
|||||
|
|||||
墓前に机(お供え台)を準備し、お盆を用意し 半紙を敷いてその上にお供え物を並べる。 (机は、石材店がご用意します。) |
|||||
|
|||||
| |
服装については、礼服が無難ですが、 黒や、紺の派手でない服装なら良いようです。 |
||||
|
|||||
| |
関西では、故人のお骨を納骨袋に移し、 納骨室に安置します。 納骨袋は、石材店がご用意します。 |
||||
|
|||||
| |
ご僧侶の指示により、各自ご焼香をする。 | ||||
|
|||||
| ※法要後は、列席者で会食を行います。 | |||||
| お布施あるいは、御経料としてお包みしましょう。ひとつにまとめないで、 お布施・お車代・お膳料(法要の後に僧侶が、会食に参列しない場合)等と分ける方法もあります。 金額的な事は、最近では、お寺様にお尋ねすると割にざっくばらんに教えて頂ける所も多い用ですが、なかなかお聞きしにくいことですね、お寺様とのお付き合いの仕方によって又、地域によって多少違いますが、 一般的には3万円〜5万円位が多く、所によっては8万円ぐらいといわれる所もあります。 |
||
| 霊園によっては、届け入れ書等のフォームに違いはありますが、 次のような物が必要です。 ・火葬許可証・霊園使用許可書・霊園の届け入れ書・認めの印鑑 |
||
| お墓を立てるというのは、お祝い事なので、 紅白の水引に建墓お祝いなどと書かれるのが、一般的です。 |
||
| フリーダイアルでお気軽にお問い合わせください! | 安心3つのお約束 | ||
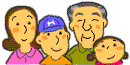 |
|
|
|
| fwht5854@nifty.com | |||
| 新着情報 ご挨拶 会社案内 近江大霊園 公営霊園情報 優良霊園紹介 お買い得墓石 御見積から完成まで CAD集 施工例 ご提案イメージ&完成写真 工事写真 メモリアルローン お墓Q&A 開眼法要について 戒名追加彫刻 お墓のお引っ越し メール リンク プライバシーポリシー |
| e-mail:fwht5854@nifty.com Copyright(C)2002-2015 Tozai Bussan Co.,Ltd.All right reserved. |